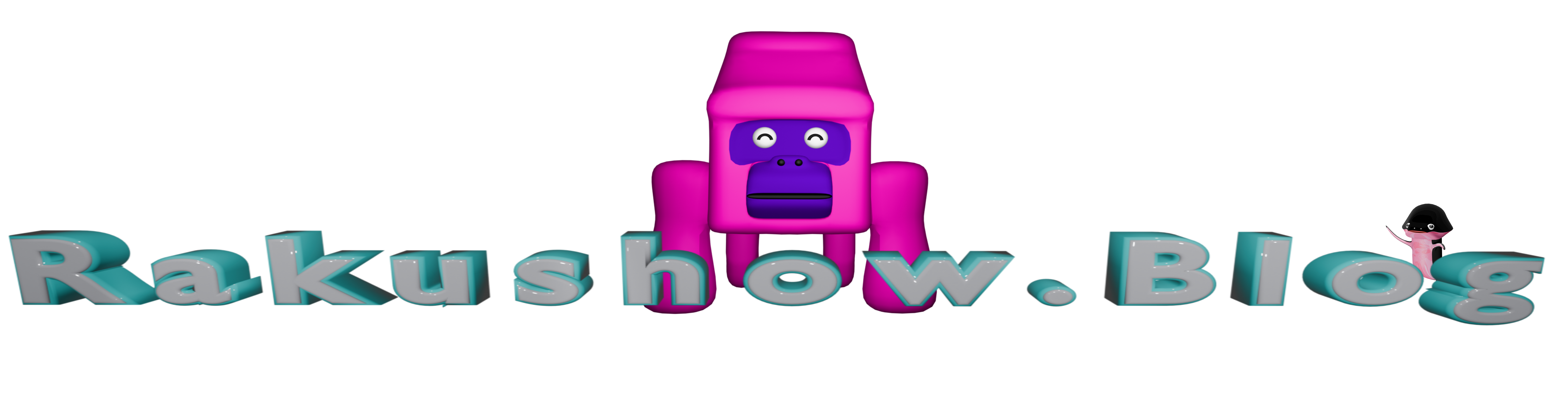比良山地に存在する池塘巡り。
奥山に標高1,000m弱の窪地に突如として現れる水瓶こと池塘。只々不思議な現象である。
そんな池塘(高層湿原)を今回も巡ってきた。
比良山地(琵琶湖の西側)には数多くの池溏・高層湿原が大小点在している。
湿原について
まず、湿原・池溏とはなんじゃろか?ってところから、堅苦しくなく記述していく。
びっくりするくらい各所・各領域・各類で表現や定義が違う😆😆😆
徐々に広範囲にわたる情報を、狭義に煎じ詰めまとめてみたいと考えている。
ラ・サール条約
『第1条1 この条約の適用上、湿地とは、天然のものであるか人工のものであるか、永続的なものであるか一時的のものであるかを問わず、更には水が滞っているか流れているか、淡水であるか汽水であるか鹹水(かんすい=塩水・海水)であるかを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地または水域をいい、低潮時における水深が6メートルを超えない海域を含む』
✅️かなり広範囲な定義である。
広辞苑(第五版)
多湿・低温の土壌に発達した草原。動植物の枯死体の分解が阻止されるため、地表に泥炭が堆積している。構成植物・生態条件などにより低層・中間・高層湿原などに区分。やち。
新版地学事典(日本地誌研究所)
泥炭が堆積した上に形成される草原。泥炭地とも。一般に寒冷な気候条件の下に発達する。この条件のもとでは、枯死した植物の腐敗・分会が妨げられるので、遺体は泥炭となって堆積し、その上に次々と草原が生育していく。低層湿原(low moor)・中間湿原・高層湿原(high moor)などが区別されるが、低層湿原ではヨシ・スゲ類など、高層湿原ではミズゴケ・ヌマガヤ・ホロムイスゲなどが特徴的。
地形学事典(町田貞ほか編集/二宮書店/1981年)
湿地草原で、その性質から高層湿原・低層湿原・中間湿原に大別される。高層湿原は寒冷多湿の地域に育成するミズゴケによって形成され、水分の供給は雨水だけである。貧栄養・強酸性のミズゴケ泥炭上にはヒメシャクナゲ・ツルコケモモなどの矮性低木がその間の停水にはヤチスゲ・ホロムイソウなどの草木が生える。
建設技術者のための地形図読図入門(鈴木隆介編/古今書院/1998年)
植生にほぼ全面覆われた湿地であり、湿った草原であり、地形種ではなく、生物学的分類用語である。地下水面から湿原の地表面までの高さによって、高層湿原、中間湿原及び低層湿原に大別される。
泥炭地と湿原:
湿原は、湿地における植生の状態をいう生態学的用語であり、地形学的には隠蔽物質の状態を示す用語である。それに対して、泥炭は堆積物の名称であり、泥炭地は泥炭を整形物質とする土地を指す用語である。多くの湿原は泥炭地あるが、泥炭のない湿原もあれば湿原になっていない泥炭地もある。つまり、湿原と泥炭地は類義語であり、同義語ではない。
✅️地形・地質・植物など様々な専門分野の方々の関連文献を読み漁り、大きく、『湿地上に成立したすべての植生を湿原≒泥炭地』と『湿原≠泥炭地』の2つの思考があることがわかった。どちらが正しいのか、または正すべきなのかはわからないが、研究領域によるものであり、本稿ではその辺りについては、“ラフ”に記述していきたいと考えている。
※泥炭とは? 過湿条件下で十分に分解しない植物遺体が堆積したものである。土壌学的観点からは泥炭土と呼び,有機質土壌の一つとする。この堆積地が泥炭地である。
湿原の種類
種類についても、各研究領域により、様々な考え方が現存している。
ざっと数えてみても、植物分類学・生態学・地理学・社会学、植生学、自然地理学、構造地質学などなど。。。
自分なりに整理し、まとめてみる。
まずは、
・低層湿原
・中間湿原
・高層湿原
の3タイプに区分される。低層、中間、高層の漢字から推測される通り、周囲との高さの関係によって判断することができる。湿原は、常に植生の枯死と堆積を繰り返しており、低層から中層、高層湿原、陸地へと変化し、堆積のスピードは上層で、年に1mm程度ととてつもなく永い永い時間が経過し、その姿を変えていく。
「湿原≒泥炭地」と考えると、
・低位泥炭地
・中間泥炭地
・高位泥炭地
とも定義できる。


写真・図ともに、左から「低層湿原」、「中間湿原」、「高層湿原」。
●低層湿原:水草などが枯れて泥炭になり、堆積していく。
●中間湿原:周りの土地の地下水面と同じか低い状態から、更に泥炭が積み重なっていく。
●高層湿原:泥炭が積もり続け湿原が盛り上がり、周りの土地よりも地表面が高くなった状態。
また、湿原を形成する上で大きな役割を果たす土壌環境を主に考えた場合、2パターンに区分される。
・泥炭湿原
・鉱質土壌湿原
泥炭湿原
泥炭とは、過湿条件下で十分に分解しない植物遺体が堆積したものである。土壌学的観点からは泥炭土と呼び、有機質土壌の一つである(上の写真・図ともに泥炭湿原のプロセスを模ししたものである)一般的に泥炭湿地は湖沼、河川の後背湿地、低温で排不良の山地斜面などを起源とし、湿原を涵養する水は、泥炭堆積の序盤においては、比較的富栄養な地下水・地表水であるが、堆積が進んで地盤が上昇すると、貧栄養な雨水へと変化する。これと並行して、植生も移り変わっていく(湿性遷移)
●湿原に多く見られる形態。
●数千年規模の単位で形成される。
●植物の生産量が、堆積物の分解量にまさるときに形成される(堆積速度はおよそ1mm/年程度)
陸化型
もともと池・沼・湖(湛水地)であったところに周辺部から土砂がたまり、浅くなった箇所から植物が生えるようになります。寒冷地ではその遺体が泥炭として堆積し、さらに水深が浅くなり、湖は泥炭で埋め尽くされ湿原となる。その後も堆積を続け高層湿原となり最終的に陸地と変化していく。
沼沢化型(しょうたくかがた)
扇状地の下側から水が湧き出すことにより、水分がたまったところに植物が生え、それらの遺体が泥炭として堆積し湿原となる(湿潤化または沼沢化)
後背湿地型(こうはいしっちがた)
河川が増水し氾濫が起こった後、河川の両側にはその名残として水分が溜まり、これを後背湿地と呼びますが、そのような箇所の水はなかなかなくならず泥炭が堆積し湿原となります。
鉱質土壌湿原
鉱質土壌湿原は、立地基盤に泥炭がまったく存在しないか、植生遷移に関与しない程度のわずかな堆積しか認められない湿原である。鉱質土壌湿原は、湧水湿地と呼ばれる。貧栄養な浸出水が地表をゆっくりと斜面を流下し、湿潤化することによって形成される小面積の湿地に主に成立する。
・面積が小さい
・湧水の発生とともに短時間で形成される
・植物遺体が速やかに分解を進め、堆積物が集積しにくい。
・丘陵斜面に形成されることが多い。
・西日本の暖温帯に広く分布。
谷壁型(こくへきがた)
谷壁型は谷壁斜面や段丘崖のような傾斜地に成立し、斜面上部から湧出した地下水が地表面を面的に
広がって(発散)移動することで湿潤な環境を形成する。
谷底型(たにぞこがた)
谷底型は谷底面や堤間低地のような谷地形や凹地に成立し,地下水が凹地に向けて収束することで湿潤な環境を形成するタイプである。
疑似型
本来は泥炭地湿原であるところが、火山活動や洪水などにより急激に鉱質土壌によって埋積されて形成された一時的な鉱質土壌湿原。
✅️表にまとめるとこんな感じでしょうか。
| 泥炭湿原 | 鉱質土壌湿原 | |
| 主な水源 | 雨水、霧 (周囲の地下水とは切り離されている) | 地下水、湧水、河川水 (周囲の山地からの水が供給される) |
| 土壌の性質 | 酸性、貧栄養 | 中性~弱酸性、富栄養 |
| 主な植物 | ミズゴケ類、イソツツジ、モウセンゴケ、ワタスゲなど | 湿性植物、抽水植物、カヤツリグサ科植物 |
| 形成メカニズム | 泥炭が積み重なり、泥炭が積み重なり、巨大なスポンジとなって雨水を保持し、斜面を這い上がる | 地下水や湧水が谷壁に沿って常時供給され、湿潤な環境を形成する |
実際の比良山地に点在する高層湿原・池溏はどういった分類の属するのか???
比良山地の高層湿原・池溏はどの分類なのか?
『この山地は東西両側を断層 に起因する直線的な急崖に挟まれた典型的な地塁山地で、標高1,000m前後には準平原遺物と思われる小起伏地が見られ、八雲ヶ原の高層湿原も存在している。この小起伏地の標高は、隣接する朽木山地のそれより200mほど高く、花折断層を境として比良山地の部分が不等隆起した結果を示すものと考えられている』
出典:「滋賀県の地形区区分・滋賀大学 小林健太郎氏」
※準平原遺物とは
「国土地理院_その他の地形」より
「国土地理院_比良山地_3D」より
※小起伏地とは
起伏量200mm以下の部分が卓越する山地と丘陵。
✅️湿原を形成させるためには、もちろん地形・地質を考えなければならない。
「小平坦面となって残っているもの」というのが大きく起因するものではないかと推測できる。
「八雲ヶ原湿原」、今回の白滝山麓にある「四つの池溏と高層湿原」についても、“泥炭湿原”と呼べるのではないのかと考えられる。
今回様々な関連文献を読み漁り、著者も非常に勉強になり、更に山が好きになった。
次の山行時には観察する観点が変わってきそうなのが愉しみである。
※専門分野ではないために、誤記ならびに誤認が生じる箇所が確認された場合は、遠慮なくご指摘いただければ幸いです。
ウンチクばかりの長々文章に疲れた方は、下記の山行動画を拝見いただければ幸いです。
地衣類について
最後にもう一点、
動画途中に出てきた半分コケ生した岩について解説します。

なんか不思議だと思いませんか???
半分はコケに覆われていて、半分は覆われていないこの現象。もちろんコケの群生を進めている最中かもしれないのだが。
実はこれコケに覆われていない石の表面には、「地衣類」と呼ばれる菌類と藻類が共生して一体となった別の生物が付着している可能性があります。

出典:「浜松科学館」より
目に見えて、わかる種類のものもあれば、拡大鏡や顕微鏡で覗かないと見えないものもあるようで、地衣類とコケは、岩や樹皮の上という同じような環境で生きているために、限られたスペース(領地)を奪い合って競合している。地衣類は成長が非常にゆっくりなために、成長のはやいコケに覆われてしまう。そこで地衣類は、コケの生育を阻害する化学物質を出し、コケが生えてくるのを防いでいると考えられている。
非常にオモシロイ現象である😁
戦国時代さながらである(アッパレ❗️❗️❗️)
【出典】
・Google map
・Google Earth
・「環境省 湿原データセンター」より
・「国土地理院 湿原・湿地の定義に関する参考資料」より
・「山地湿原の発達史と古環境 叶内敦子氏」より
・「滋賀県の地形区区分 小林健太郎氏」より
・「湿原の環境と土壌 富田啓介氏」より
・「湿原の形成過程について 堀正一氏」より
・「泥炭地の特性と湿原植生 冨士田裕子氏」より
・「日本に見られる鉱質土壌湿原の分布・形成・分類 富田啓介氏」より
・「日本の重要湿地 環境省」より
・「第5回自然環境保全基礎調査 湿地調査報告書 環境庁自然保護局」より
・「浜松科学館」webサイトより